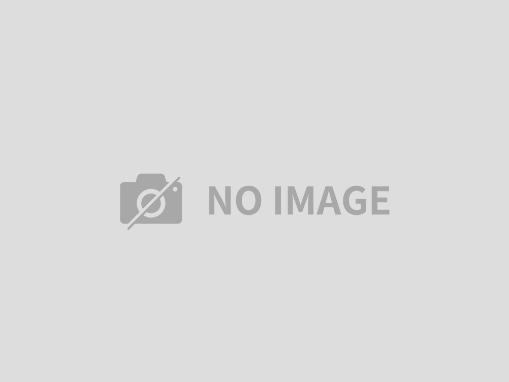講演活動/合理的配慮研修
どんな研修が可能ですか?
障害の社会モデルや障害者差別解消法、合理的配慮など、障害に対する考え方や社会のあり方について、わかりやすくお伝えします。また、私たちが実践する障害のある人たちがどのように自立生活を実現してきているのか、その想いやそこに至るまでの過程や支援について、当センターでの活動の取り組みなど。そして障害者運動の歴史や意義についてもお話しできます。
講演内容は、対象となる方々の年齢や立場(小学生から大学生、地域の住民、企業・行政職員など)に合わせて、わかりやすく、ご依頼者様のニーズに合わせてお話します。
障害者のライフストーリーと自立生活
障害と向き合ってきたこれまでの人生(自分史)を振り返りながら、なぜ自立生活が必要で、どのように自立生活を実現してきたのか、支援や制度をどう活用してきたのかをお話しします。「生まれたときから」「学校生活」「家族との関係」「施設や入院生活を経て」「地域で自立するまで」といったリアルな体験を通じて、自立することの意味や、誰もが地域で生きる権利について、改めて考えることができるようなお話をします。
障害の理解と社会モデル
障害についての基本的な理解を深めるとともに、「障害は本人の問題ではなく、社会の側にある」という社会モデルの考え方をわかりやすくお伝えします。
日常にあるバリアや無意識の偏見に気づき、誰もが暮らしやすい社会を一緒につくっていくためのヒントを届けます。
障害者差別解消法と合理的配慮
障害者差別解消法の目的や背景、そして「合理的配慮」とは一体何なのかについて、具体的な事例を交えながらわかりやすくお伝えします。
障害のある人が直面する見えにくい壁や、配慮がないことで生まれる差別について知り、どんな配慮が求められているのかを一緒に考えます。
法律の知識だけでなく、日常の中で私たち一人ひとりができる行動のヒントも紹介し、誰もが対等に生きられる社会を目指すための一歩を踏み出すきっかけにしていきます。
リアライズの活動紹介
自立生活センターとはどのような役割を持つ場所なのか、そして障害のある当事者たちがどのように地域の中で活動しているのかを、権利擁護やバリアフリー推進、地域づくりなど、具体的な取り組みとともにご紹介します。
活動実績
自治体及び教育委員会
大阪府、京都府、和泉市、貝塚市、忠岡町、大阪狭山市、河南町、太子町、千早赤阪村、箕面市、摂津市、茨木市、亀岡市、国際関連
大学専門学校等
大阪河崎リハビリテーション大学、大阪芸術大学、大阪公立大学、関西医療大学、関西大学、四条畷学院大学、常磐会短期大学、奈良教育大学、南海福祉看護専門学校、桃山学院大学、和歌山大学
小・中・高等学校
小学校(泉大津市、和泉市、京都市)、中学校(泉大津市)、高等学校(大阪府、京都府)(合計30校超)
企業及び団体
大阪及び京都に所在する一般企業及び福祉事業者、公益団体等